普段は精密部品をミクロン単位で制御している
ロームのエンジニアたちが、
まさかの“巨大ブランコを走らせる”という
挑戦に立ち向かった。
スケールも発想も桁違いのものづくり、
その舞台裏に迫る。
-
リーダーJ.Kトウ -
M.Sダ
設計担当 -
Y.Kミツ
制御担当 -
M.Mダ
リモコン担当 -
S.Iムラ
設計担当 -
T.Eスミ
制御担当 -
N.Nグチ
設計担当 -
T.Aマコ
設計担当
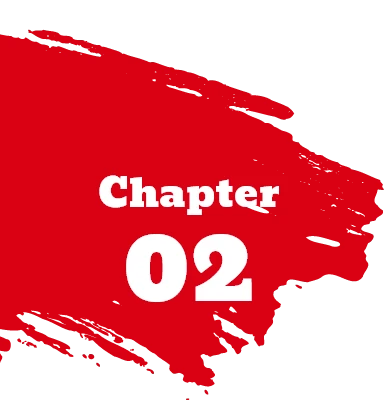
「“ブランコ・デ・R”誕生秘話」
「“ブランコ・デ・R”誕生秘話」
―マシンのコンセプト「ブランコを大きく振って、
反動を抑えながら最速で前進する」をどのように
実現しようとしましたか?
“ブランコらしさ”と“速さ”の両立に挑戦
-
M.Sダ お題が発表されたときは、「ブランコを走らせる?しかも駆動源を持たせちゃダメ!?」と頭を抱えましたね。
-
Y.Kミツ 電気制御担当としても、どうやって設計すればいいのか本当に悩みました。
-
M.Mダ でもアイデア自体は最初からたくさん出ましたよね。案を取捨選択していく過程で、リーダーが「自分はやっぱりブランコらしい形を実現したいんだ」という熱い想いを語ってくれて。それで方向がバチッと決まっていったのが印象に残っています。
-
M.Sダ リーダーのこだわりをカタチにするためにさまざまな方法を模索しましたよね。ただ、「ブランコらしく揺れる」と「早く走る」を両立させるのが本当に難しかった。
-
S.Iムラ 揺れの力をどう前進に変えるか、反動をどう抑えるかという課題に対して、試作と実験を何度も繰り返しましたね。その中から実現可能性の高い3案に絞り込み、さらに2案を実スケールで試作して設計や素材を調整していきました。
-
M.Sダ 最初はブランコの重心を可変にして、巻き上げ機構で前後の重心を変えながら前進力を取り出す案を考えました。でも構造が複雑で、モータトルクや制御的にも難しそうだった。そこで重心を上下ではなく前後に動かして負荷を抑え、できるだけ長く揺らし続けることで前進エネルギーを取り出す方向に切り替えました。機構はシンプルな「ワイヤードラム巻き取り機構」に。これが本番で使われました。
-
S.Iムラ それにしても、今回制御チームは本当に大変でしたよね。普段ならメカ設計の構想が終わってから制御設計に入りますが、今回は並行作業。ときには制御が先に進むこともありました。メカ担当として、正直すごいなと思っていました。
-
Y.Kミツ 「どんな動きになりそうか」は事前に聞いていたので、小さな板をブランコの座面に見立てて、手で振りながらイメージしていました。座面を振ってみて値がどんな時にどう変化するのか、どうやって戻りを検知するのか。地味に机の上で小さな板を振りながら、パソコンをカタカタと。はたから見たら「アイツ何してるんや?」って思われていたかもしれません(笑)。
-
M.Mダ リモコン班も、アイデア出しの段階から先行して動いていました。リモコンは動いて当たり前という存在。だからこそ、どんな状況でも確実に機能するものをつくらなければいけません。「どんな機構になっても動かせるリモコンであること」を意識し、安定して動くことを最優先に、限られた時間の中で制作を進めました。
―形にするまでにどんなところに苦労しましたか?
どんな工夫で乗り越えましたか?
試行錯誤の連続が生んだ、チームの結束と個の力
-
M.Sダ 壊れずに完走させるためには、ブランコのエネルギーを無駄なく推進力に変えつつ、剛性をどう確保するかが課題でした。最初は補強をしっかり入れて強固なフレームを組んだところ、見事に予算オーバー(笑)。そこから必要最低限まで軽量化しました。でも、補強を外しすぎて「あ、ここ外しちゃダメだった!」ってこともありましたね。
-
M.Mダ 1回、外しすぎてブランコなのに座れないときもありましたもんね(笑)。
-
S.Iムラ 部品の調達は一番の難関でした。予算が限られていたので、どうコストを抑えながら強度を確保するかに頭を使いました。ステアリングなど強度が必要な部分は金属を使い、それ以外は3Dプリンタで自作。これが思いのほかうまくいって、普段の業務ではあまり使わない技術に挑戦できたのは大きかったです。
-
Y.Kミツ 私はブランコの動きを制御に落とし込むのに苦労しましたね。普段フローチャートを書くときは、「こう動かしたい」という明確なイメージがあるのですが、“ブランコをどう動かすか”なんて経験がない(笑)。まったくイメージが湧かない中で、実際にブランコの動きを一つずつ図に描き起こし、「この状態のときはこう動く」「次はここに移行する」といった流れを地道に整理していきました。ブランコの角度や勢いによって求められる動きが違うので、状態ごとに整理しながら、それぞれに合わせたコードを書き分けていきました。
-
M.Sダ ブランコの紐が柔らかいので、振るとどうしてもたわみが出て、思ったように前進してくれなかったですよね。制御もうまく狙い通りに動かず、時間もない極限の中で最後は「もうY.Kミツさんに任せるしかない」という場面もあったけど、プレッシャーは感じませんでしたか?
-
Y.Kミツ その時はもう必死で、全然感じてなかったです(笑)。「なぜこれが動かないんだ」って、そればかり考えてました。動かない要因を一つずつ潰して、絶対に止まらないようにコードを仕込んで。没頭していましたね。精神的には、ひたすら「大丈夫、やれる」と自分に言い聞かせながら進めていました。でも、みんなが「ブランコを完成させる」という同じ目標を持って、それぞれの持ち場で全力を尽くしてくれていた。その姿を見るだけで不思議と安心できて、自分も自分のやるべきことに集中できたんだと思います。
-
S.Iムラ リモコン班も安定した操作を実現するためにかなり工夫していましたよね。
-
M.Mダ そうですね。本番の会場では、撮影のために多くの無線通信が飛び交っていることはわかっていました。過去の競技で通信が途切れてマシンが止まってしまうケースもあったと知り、「それだけは絶対に避けたい」と思っていました。ただ、実際の電波環境がどうなるかは想像できない。だからこそ、できる限り遠くまで安定して通信できる方式を探し、何度も試作を重ねました。通信距離が長いほど安定はしますが、応答速度が遅くなるという課題もあって。特にステアリングは即応性が求められるので、そのバランスを考えました。最終的には25mのコースに対して余裕を持ち、30~50mの距離でも安定通信でき、1ミリ秒単位で反応できるものを目指しました。
―今回の挑戦で印象に残っていることを教えてください
ものづくりが好き、その原点に立ち返れた
-
M.Sダ 私は中途入社でまだ社歴が浅く、普段は他部門の方と関わる機会がほとんどありませんでした。今回、さまざまな部署から集まったメンバーと一緒に取り組む中で、「こんなにすごい人たちが社内にいたんだ」と素直に感動しましたね。それぞれ専門も担当業務も異なるメンバーが協力し合えたことで、「こんなふうに力を合わせれば、もっといいものづくりができる」「組織としてももっと良くなれる」という期待が生まれました。せっかくつながれたこの縁を大切に、今後も良き相談相手として関係を続けていきたいです。
-
一同
よろしくお願いします!
-
M.Sダ また、限られた期間で結果を出さなければならないスピード感や、失敗が許されない緊張感は、日々の業務にも通じるものがありました。この貴重な経験を糧に、これからの仕事にもスピード感とチーム意識を持って取り組んでいきたいと思いますね。
-
Y.Kミツ 他の部門と一緒に仕事をする中で、文化や考え方の違いを感じることもありましたが、自分の意見を伝えると相手がちゃんと受け止めてくれる。逆に相手の考えも聞いて、「なるほど、そういう見方もあるのか」と思うこともありました。そういうやり取りができたのが本当に良かったなと思っています。普段の業務でも他部門と関わることは多いので、この経験は今後にも生かせると感じています。今でも、ブランコが初めて動いたあの瞬間をはっきり覚えていて。あのときの光景が頭の中で何度もフラッシュバックしてくるんですよ。僕がものづくりをしている理由って、きっとあの瞬間のためなんだろうなって。ちょっと熱すぎますかね(笑)。
-
M.Mダ すっごくわかります!
-
M.Mダ 本当にね、あの瞬間こそがものづくりをやっていて一番楽しい時なんですよね。
-
M.Mダ 私は入社2年目で、チームの中でも経験も知識も浅い方でした。普段の業務では、同じ部署でも関わりが少なく、他部署となるとほとんど接点がありません。そんな中で、今回は全員が“魔改造初心者”という同じ立場で、技術だけでフラットに話ができたのが新鮮でした。普段は少し壁を感じるような先輩方とも、ものづくりの話になると一気に距離が縮まるんです。みんな根っからの“ものづくり好き”だから、オタク談義のように盛り上がって(笑)。そんなふうに、部署や立場を超えて技術の話でつながれる関係が築けたのは、とても貴重な経験でした。「他部署の人でも、怖がらずに話しかけてみれば何とかなる」という実感を得られたことが、一番の収穫かもしれません。今後の業務でも、この経験を生かして、積極的にコミュニケーションを取っていきたいと思います。
-
S.Iムラ 年齢も役職も関係なく、みんなが一つの目標に向かって意見を出し合う空気がとても良かったと私も思います。この活動では“自分たちで考えて動く”という醍醐味を実感しました。アイデアを形にする難しさと面白さを改めて感じられたし、誰も経験のない挑戦に全員が本気で向き合う、そんな環境が本当に刺激的でした。今回の取り組みを通じて、エンジニアとしての自分の力が底上げされたと感じています。今後はこの経験を糧に、より実効性のある提案や、部門をまたいだ連携にも積極的に挑戦していきたいと思います。「みんなでつくる」ことで生まれる力を、これからの業務でも発揮していきたいですね。
Extra Chapterでは、
本番を走ったモンスターの陰で奮闘していた
もう一つの開発チームに焦点を当てます。
そこには、悔しさの涙とともに、
確かに受け継がれた情熱がありました。
